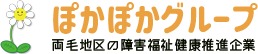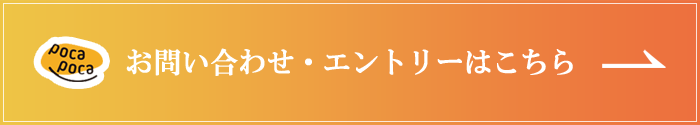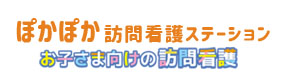子どもの偏食への理解と家庭支援のあり方
〜安心できる「食」の体験づくりを目指して〜
発達に特性のあるお子さんや、感覚に敏感な子どもたちにとって、「食べる」という行為は簡単なことではありません。放課後等デイサービスや児童発達支援の現場でも、「偏食」に関する相談や支援はよくあるテーマです。
今回は、福祉支援員として子どもの偏食にどのように向き合い、家庭と連携しながら支援していくかを考えてみたいと思います。
偏食は「困りごと」ではなく「特性」や「発達段階」
支援の現場では、「食べない=わがまま」と捉えるのではなく、**感覚や認知、経験に基づくその子の“特性”**として理解する姿勢が求められます。
-
味やにおい、食感に対する過敏さ
-
食事への不安やこだわり
-
新しい物への抵抗感(新奇性恐怖)
-
過去のネガティブな食経験の影響
このような背景をふまえ、「なぜ食べられないのか」を一緒に考える視点が大切です。
福祉支援員としての対応ポイント
1. 安心して食べられる環境づくり
無理に食べさせるのではなく、「見慣れる」「触ってみる」などの段階的な関わりを大切にします。楽しい雰囲気の中での食事や活動が、子どもたちの安心感につながります。
2. 食育や調理体験を取り入れる
食材に触れる体験、調理過程への参加などを通して、「食」への興味・関心を育むことができます。自分で関わった食材は、少し食べてみたくなる気持ちにつながることも。
3. 成功体験を積み重ねる
「今日はスプーンを近づけられたね」「ちょっとにおいをかげたね」など、ほんの小さなステップを見逃さず、できたことを肯定的にフィードバックすることが大切です。
4. 他の栄養素での代替も視野に
一つの食材にこだわらず、「同じ栄養を別の食べやすい方法で摂れていればOK」という柔軟な考え方を持つことも重要です。
保護者支援・連携のポイント
子どもの偏食について、家庭でも悩まれている保護者は少なくありません。支援員としてできることは、「責める」ことではなく、「寄り添い」「情報を共有する」ことです。
-
「園や施設でも無理に食べさせていません」
-
「今日、少しだけチャレンジできた様子がありました」
-
「今は苦手でも、いつか一口食べられる時が来ると信じています」
など、安心できる声かけを心がけましょう。保護者の不安を軽減し、一緒に見守る関係性を築くことが大切です。
まとめ:その子の「ペース」を大切に
偏食への支援は、「克服する」ことを急ぐよりも、「その子らしい食との関わり方」を育てていくことが大切です。福祉支援員として、子ども一人ひとりのペースや特性を理解しながら、安心して食と向き合える環境をつくっていきましょう。
食を通じて、「できた!」という自信が生まれ、その子の世界が少しずつ広がっていく――そんな支援の在り方を、私たちが一緒に支えていけたらと思います。
関連記事
-
 2023.10.09 雨の日の運転に注意!交通事故を予防しよう
2023.10.09 雨の日の運転に注意!交通事故を予防しよう -
 2023.09.20 充実した仕事人生を実現するためのヒント
2023.09.20 充実した仕事人生を実現するためのヒント -
 2023.05.20 重度障害者の日常生活―グループホームで共に学ぶ
2023.05.20 重度障害者の日常生活―グループホームで共に学ぶ -
 2023.05.02 休暇で学ぶ!スキルアップを目指して
2023.05.02 休暇で学ぶ!スキルアップを目指して -
 2024.01.08 信頼と責任を築く重要な要素
2024.01.08 信頼と責任を築く重要な要素 -
 2025.04.04 【春休み特別企画】ぽかぽか広場の外出支援と遊びを通した療育
2025.04.04 【春休み特別企画】ぽかぽか広場の外出支援と遊びを通した療育