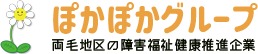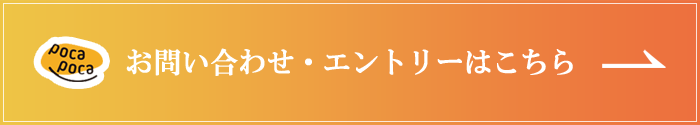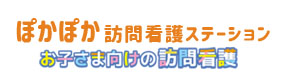障がい児を育てる──大変さとその中にあるかけがえのない日々
◆ 毎日の大変さ、どう向き合うか
障がいを持つ子どもを育てることは、健常児育児とはまた異なる大きなチャレンジに満ちています。朝の支度や療育、通院、リハビリなど、時間的にも体力的にも、そして精神的にも負担が重なる日々。とくに最初の数年は、
「他の子より頑張っているのに追いつけない」「自分だけがこんな思いを抱えているのでは…」
といった深いストレスを感じることも少なくありませんでした。社会的な偏見や、周囲との違いに戸惑う不安も、当事者でなければ理解し難いものがあります。
◆ 心と体を守る“支え合い”の輪
孤独と不安に押しつぶされそうになるとき、地域や支援団体とのつながりが、どれほどの救いになるか計り知れません。育児サークルに参加し、同じ悩みを持つ親との出会いから、
-
情報交換の場
-
心の支え
-
子どもの社会性向上の機会
-
レスパイトケアや休息のヒント
など、多くの効果が得られるといいます
また、行政やNPOによる専門的サポート(福祉手当、医療費助成、補装具助成など)は、経済的負担を軽減し、心の余裕を取り戻す大切な柱となっています
◆ 支援を受けて生まれる“ゆとり”
「全部自分でやらなければ」という思いから解放されることが、親の心を軽くします。夫婦が役割を分担し、周りに頼ることで、
「親が健やかでいると、子どもも幸せ」
という言葉が現実味を帯びてきます。
心が疲れたときこそ、レスパイト(短期預かり)を利用したり、ソーシャルワーカーに相談したり、外の世界とつながることで、少しずつ「持ちこたえられる」心の基盤が築かれます
◆ 小さな成長がもたらす“喜び”
だからこそ、療育や日々のリハビリを地道に積み重ねる中で、
-
「ふだんできなかったことが、少しずつできるようになった」
-
「見通しが立つことで癇癪が減り、自信をつける姿に感動した」
といった喜びが何よりの生きがいになります。
「生きがいとは“自発的に取り組み、達成感を感じること”」とする考えにも通じ、子どもの小さな一歩が、親自身の“生きる意欲”へとつながっていきます
◆ 親が“自分自身”を大切にすること
障がい児育児では、親自身の心が不安定になると、子どもとの接し方にも影響が出ます。まずは親自身が
-
自分の感情や価値観を言語化する
-
“自分”を理解する時間を持つ
ことで、子どもの内面を理解し、適切なコミュニケーションがとりやすくなるようです
◆ まとめ:共に歩む毎日を、ひとつずつ
-
一人で抱え込まない
支援を受け、仲間や専門家とのつながりを築いていく。 -
小さな成長に目を向ける
「成長したね」の言葉が、親子の日常を豊かにする。 -
親自身の“ゆとり”を大切に
自分の時間や心のケアが、より良い育児環境を作る。
障がい児育児は、大変さと不安の中にあっても、愛情と支援があれば、豊かな日々を刻んでいけます。あなたも、ぜひ小さな「できた!」を積み重ねながら、ご自身とご家族を大切にして前を進んでいってください。
関連記事
-
 2025.01.29 地元で働くことの意義と地域貢献
2025.01.29 地元で働くことの意義と地域貢献 -
 2024.01.09 子どもたちの未来を担う日本の可能性
2024.01.09 子どもたちの未来を担う日本の可能性 -
 2024.03.06 子ども支援現場からの地域貢献 ― 未来への架け橋となる活動
2024.03.06 子ども支援現場からの地域貢献 ― 未来への架け橋となる活動 -
 2023.04.11 花粉症で運動で予防! 健康な季節を過ごすために
2023.04.11 花粉症で運動で予防! 健康な季節を過ごすために -
 2023.12.11 健康と心の安寧:風邪予防とストレス管理のコツ
2023.12.11 健康と心の安寧:風邪予防とストレス管理のコツ -
 2023.11.14 個人情報コンプライアンスの重要性
2023.11.14 個人情報コンプライアンスの重要性